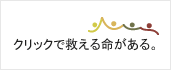奇食ハッチポッチLite2
管理人が気になった、ちょっと変わった食べ物・飲み物を紹介しています。
カテゴリー「奇食:デザート」の記事一覧
- 2025.04.17 [PR]
- 2009.05.19 チーズとうふ
- 2009.04.11 京風ヨーグルト〈八ツ橋風味〉
- 2009.04.03 みたらし団子アイス
- 2009.03.30 しば漬けアイス&シャーベット
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
京風ヨーグルト〈八ツ橋風味〉
「京風ヨーグルト〈八ツ橋風味〉」 ★★★
京都駅の土産物街(八条口のほう)で150円くらい。
八ツ橋風味なんて聞いたことないし、京都限定ぽいから買ってみた(発売元が京都の会社なので)。
もう1種類あったけど普通だったので忘れた(きなことか抹茶とか、和風の何かだった)。
原材料を見るに八ツ橋味とはシナモン味のことのようだ。
生八ツ橋は全く入ってない(入っているから美味しいということにはならなさそうだが)。
それよりは生八ツ橋にヨーグルトあんを入れた方がうまそうだ。
生八ツ橋も今は色々な種類が出ているようで、さくら、チョコバナナ、チョコイチゴ、苺、蜜りんご、黒ゴマ、八ツ橋ショコラなどがあった。
蜜りんごを買ってみたが、普通のやつのが美味しかった。
去年秋に買った栗&紫芋のがよかった。
ちなみに先日食べた七味入り八つ橋は半年の間に消滅したようだ。
ヨーグルト側面を見ると
京野菜である蕪と牛蒡を麹で発酵させたパウダーを使用
と書いてあるが、なぜヨーグルトにそんな物を入れるのかさっぱり分からない。
説明不足だ。
最近流行り(?)の植物性乳酸菌だろうか。
ヨーグルトの色はわずかにクリームがかった白。
別に八ツ橋色はしていない。
食べてみると、確かに八ツ橋の味だ。
シナモンの味なんだけど……八ツ橋と同じシナモンを使っているのだろうか?
普通のシナモン味とはちょっと違う気がする。
ヨーグルト自体は酸味が控えめで、まろやかでやさしい味。
野菜発酵パウダーのせいなんだろうか?
もちろん野菜の味は全然しなかった。
みたらし団子アイス

「みたらし団子アイス」 ★★★★★
120円。
和風冷菓子と書いてある。
きな粉餅アイスと同じシリーズ。
「やわらか白玉と醤油ソースをアイスで包んだ」と書いてある。
団子味ではなく、団子そのものをぶちこむのか。
食べてみると、バニラアイスの中からまずみたらし部分が現れ、その内側に団子がある。

外側のアイスは固めでかじるのに適したタイプ。
こないだのカステラアイスと似た味だなと思ったら、同じメーカー(maruyama)だった。
みたらしソースはみたらしそのものの味でしょっぱいので、「アイス食べてるのになんで醤油味?」と不思議な気分になる。

団子は白玉だからモチモチしている。
冷凍庫に入っていてもカチカチになっていないが、アイスに守られているせいか、それとも不凍液でも混ざってるのか?
下2cmくらいには団子が入ってなくてちょっとがっかりした。
しば漬けアイス&シャーベット

「生しば漬けのアイスとシャーベット」 ★★★
京都駅地下街CUBEで発見。
西利という漬物専門店がレストランを出していて、そこで食べられる。
420円。たけぇ。
白い方がアイスで紫がかっているのがシャーベット。
しば漬って紫のやつだけじゃなかったのか。

白い方はよくわかんない味。
わずかに糟の味がするようなしないような。
漬物臭さは全くないが、漬物はみじん切りにされた漬物の歯応えはある。
一方シャーベットの方はシソやカリカリ梅を思わせる味。
清水寺に行く途中にあった漬物屋にはシソソフトクリームが売ってたから、漬物=シソなんだろうか?
しば漬のカリカリ感もあって、こちらはなかなかうまくいっていた。
……しかし、どうして漬物をアイスやシャーベットに入れなければいけないか、食べれば食べるほど疑問は強まるばかりであった。
京漬物味わい処 西利 The CUBE (きょうつけものあじわいどころ にしり) (和食(その他) / 京都)
★★★★☆ 3.5
カテゴリー
最新記事
(11/02)
(11/01)
(10/29)
(10/23)
(10/05)
ブログ内検索
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カウンター
since 2007/oct/03